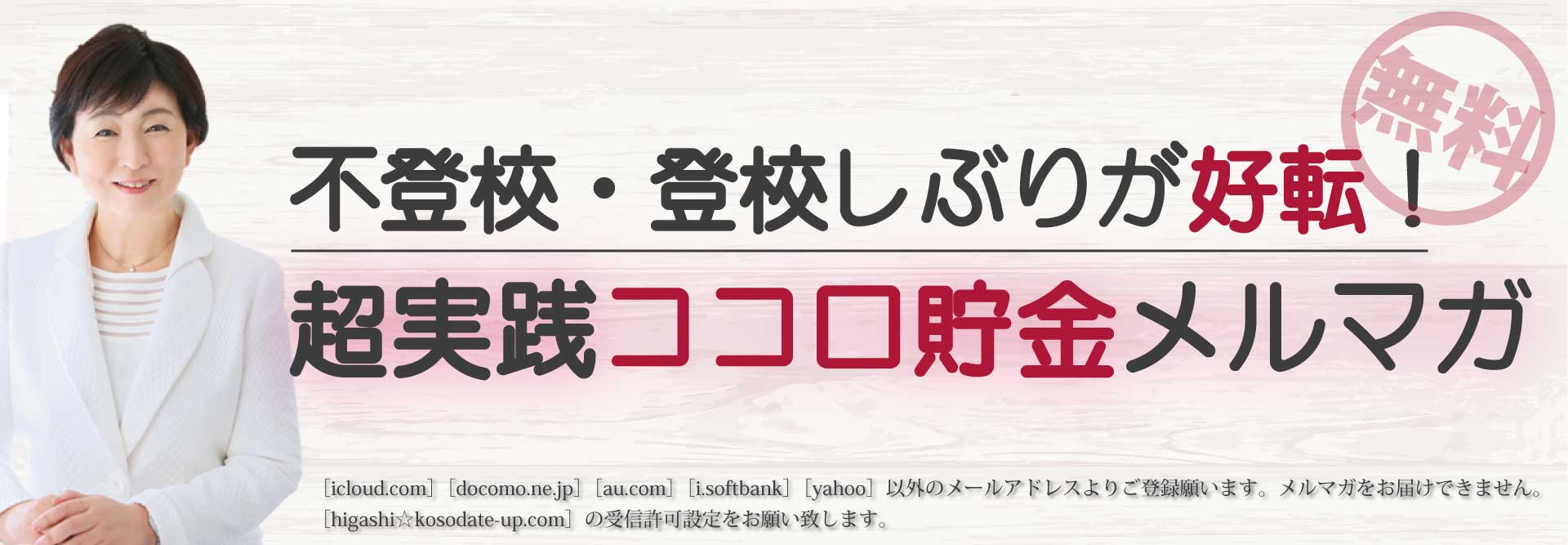◼️子育て情報◼️
◼️子育て情報◼️
子どもも、夫も夏休み・・・となると主婦は忙しいですよね。
(同意を求めてしまう。。。)
そんな時には、家族を家事に巻き込んでしまいましょう。
【コツ1】
■疑問形でお願いをする
「ここの荷物移動できる?」
「ここの掃除を手伝ってもらえる?」
と「お願い口調」+「疑問形」であなたの気持ちをうまく伝えましょう。
人間は動物の一種なので、自分が責められたと感じたら
逃げたり、隠れたり、ウソをついたり、再度攻撃をかけてきます。
【コツ2】
■具体的にお願いする
「見ていればわかるだろう・・・」という考えは甘いです。(汗)
人にはそれぞれの判断基準・価値基準があります。
とくに「片づけ」に関しては
「出しっぱなしが都合がいい派」
「全てさっぱりと収納大好き派」
「すぐに片づけたい派」
「時間がある時にやればいい派」
といろいろな派閥?があるのです。
あなたの家族が、あなたと同じ派閥とは限りません。
だから、極めて具体的に
「ここの掃除を頼んでもいい?」
「いらない物は、このゴミ袋に入れてくれる?明日最後のゴミの日だから」
とだれが聞いてもわかるように伝えます。
「自分の部屋くらい、片づけてよ!」と言っても・・・
何を、どう片づけたらいいのか?
実は、子どももパパもわかりません。
そうですね~
4歳の子どもに言うように
具体的に伝えていきましょう。
【コツ3】
小ワザです。
ママが楽しそうに片づけをします。
人は楽しそうにやっている人をみると自分もやってみたくなるのです。
子どもやパパを変えることを考えるのではなく
どんどんあなたの行動に巻き込んでいくのです。
コーチングでは、これをエンロールといいます。
わたしは、なにかとコレをよくやります(汗
片づけは、ツライものとしてやっていくと
片づけは罰ゲームになってしまいます。
そりゃ、逃げたくなりますよ。
そして、子育てだけでもとっても忙しい時期だから
一つでも片づけが済めば、OK!としてください。
きっと、カミサマは
【母になったら、全てに完璧を求めてはいけない】と
教えてくれている・・・と強く信じてみませんか??
ちなみに私は、今日はこの部分が出来た!と加点方式でやってます。

子どもは、親が「やめなさい!」ということをやります。
たとえば、調子に乗って部屋の中を走り回っているとしましょう。
ソファーの上を走ったり、ジャンプしたり、そのうちコケるのが
目に見えている・・・
はい、大人は先の見通しがつきますから、この場面の時、この先何が
起きるのかだいたい予想が出来ますよね。(^_^)v
ママ「やめなさい」
子ども「・・・・・・・・」(無視してソファの上をジャンプする)
ママ「やめなさい、いつも言っているでしょう」
子ども「・・・・・・・・・・」(ママの声を右から左に聞き流す)
ママ「やめなさいと言っているでしょ!!」
子ども「・・・・・・・・・・・」(さらにソファの上をジャンプし続ける)
ママ「やめなさいといっているでしょーーーー!!!!」
そんな時、子どもが案の定ソファーから落ちて転ぶ!
そして、泣く!
さて、そんな時あなたはどんな声を子どもにかけますか?
【普通ママ】
「そーれ、見たことか!だからママはさっきからやめなさいと言っているでしょ!」
こんな感じになりやすいですね。
普通ママは、「さっきから言っているでしょ」と正論を言いたくなります。
ただね、子どもは正論を言っても、次からそれをやめようとはしません。
特に男の子ママは、どれだけ言っても部屋の中で走り回ります。
じゃあ、そんな時、ママはいったい、どうするといいのでしょうか?
じつは、こんな時は、ママの心の器をひと回り大きくするチャンスです。
なぜなら「普通のママ」がイライラする場面ですからね。
もしも、こんな時にこう言えると子どもの次からの動きが変わります。
【穏やかママ】
【1】ママ「痛かったね」と子どもの痛みに共感する(共感するココロ貯金)
【2】ママ:痛いところを触ってあげる。(触れるココロ貯金)
【3】ママ「ソファは座るもの、ジャンプすることがダメなんだよ」
(行為を叱る)
【4】ママ「危ないからね」(理由を言う)
子育ては、「普通ママ」の心の器を広げて「穏やかママ」になる
チャンスです。
そして、「穏やかママ」になれると、子どもも自然に落ち着いてきます。
中にはとてもじゃないけれど「穏やかママ」になんてなれませんという方も
あるでしょう。
じつは、子どもは、最初からお利口さんでいるから穏やかママになれる
わけではなく、ママが「心の器」を広げることで、その「心の器」に
子どもがすっぽりと入ります。
その「心の器」を広げる作業が子育てっこと。
でもね、「心の器」を広げるって、言葉はキレイですが、それには
「心の痛み」を伴います。
だから、通常「心の器」を広げるプロセスは悩みまくり、そして
怒りまくります。
それをじわじわとサポートしてくれるのが、じつは目の前の自分の子ども。
毎日、トレーニングさせてくれます。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
ふう~、子育てって奥深い。
【自分で考えて行動出来る子ども】
そんな風になってほしいですよね。
そのためには、ママの指示・命令を減らします。
「●●しなさい!」を減らすのです。
そして、
「今、何をする時かな?」
と質問をしてみます。
「わから~ん・・・」という確率は、かなり高いです。
それは、今まで自分で考えて行動していないから。
子育ては、長期戦。
いまから、ここから。
ママのコトバが子どもをつくる
あなたは、自分のことを「どんな人間」だと思っていますか。
私たち大人でさえも、自分のことが一番自分でもわからないのです。
それくらい自分への認識は不確実です。
自分はなにものかを認識するのは、
「他者から自分のことを何と言われたのか」
という積み重ねからできています。
「人は、他者から言われたコトバでつくられている」
ということです。
ということは・・・
ママが子どもにかけるコトバかけ次第で、
子どもはどんどん変わっていくということ。
その気になって、根拠のない自信が育ちます。
たとえば、
ママよりも子どものほうが、用事を覚えていることがあります。
「明日は、早いお帰りだよ」とママが忘れていることを子どもの方が
よく覚えているとしたら
すかさず
「あなた頭がいいわね~」
「記憶力いいわね~」
と言葉をかけます。
頭がいい子を育てたいと思ったら、まず子どもの潜在意識の中に
「頭がいい子」という言葉をインプットしていきます。
ひょっとしたら、偶然覚えていたのかもしれません。(・・。)ゞ
でも、それはいいのです。
厳密にその事実を頭がいいと証明されなくても
「頭がいい子」と言われ続けたことで、
「自分は頭がいい子」
「勉強が出来る子」と認識していきます。
根拠のない自信が生まれるのです。
逆に「お前、バカだよな~」とふざけて言っていたとしても
その「バカな子」がインプットされていきます。
どの子も小学校に入学したら勉強がはじまると知っています。
例外なく、勉強ができる子になりたい と思っているのです。
それがだんだんと学年が上がるにしたがって、
少しずつ勉強が難しくなってきた時
今まで潜在意識にインプットされた言葉の違いによって、
その後を大きく左右されるのです。
「きっとできるはず」と思っていると、
子どもに不安感が少ないので、頭にスイスイと勉強が入りやすく、
逆に「バカだよな」と言われた子どもは、
「やっぱり難しい」「どうせダメなんだ」と簡単に烙印を押してしまいます。